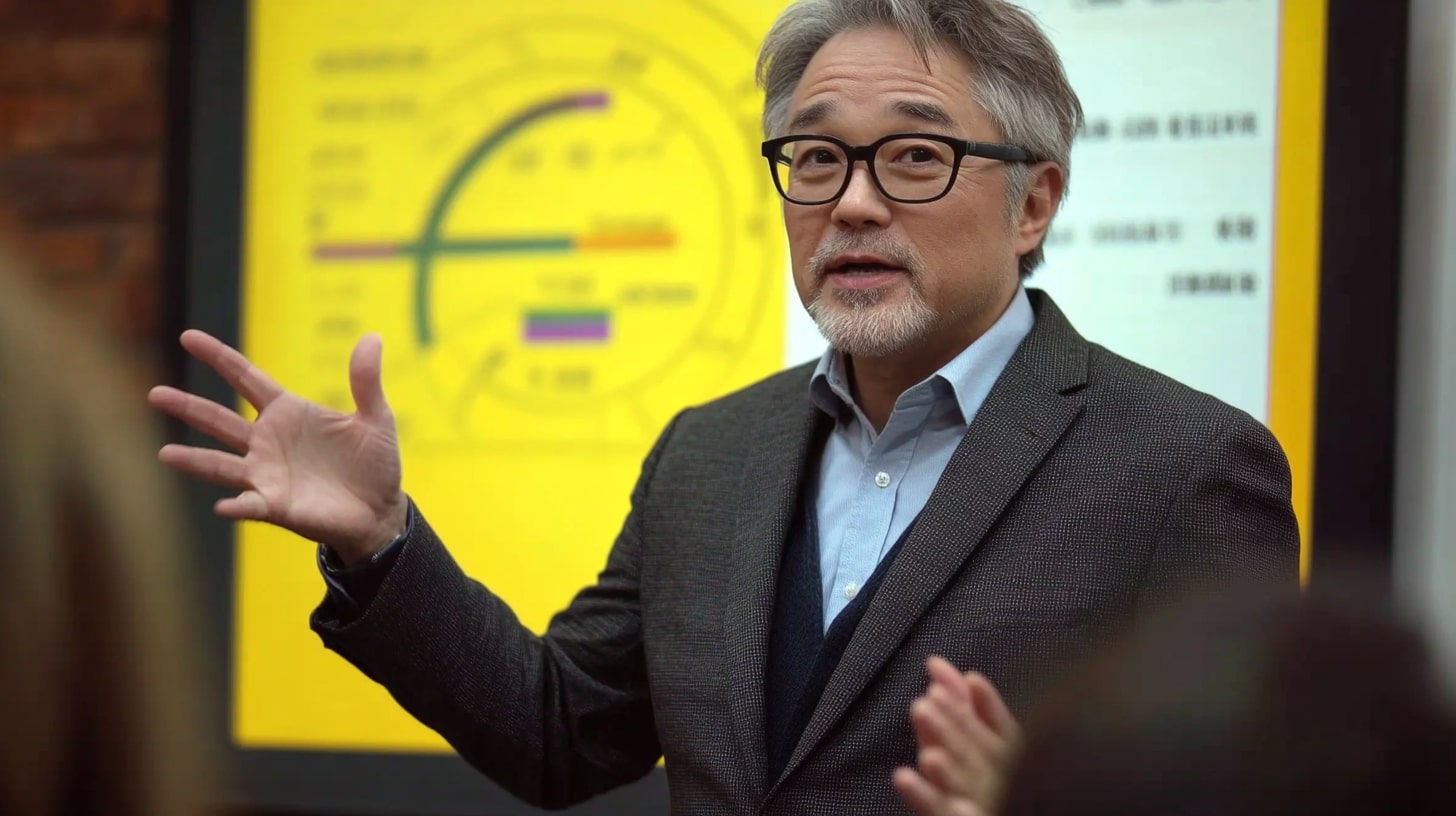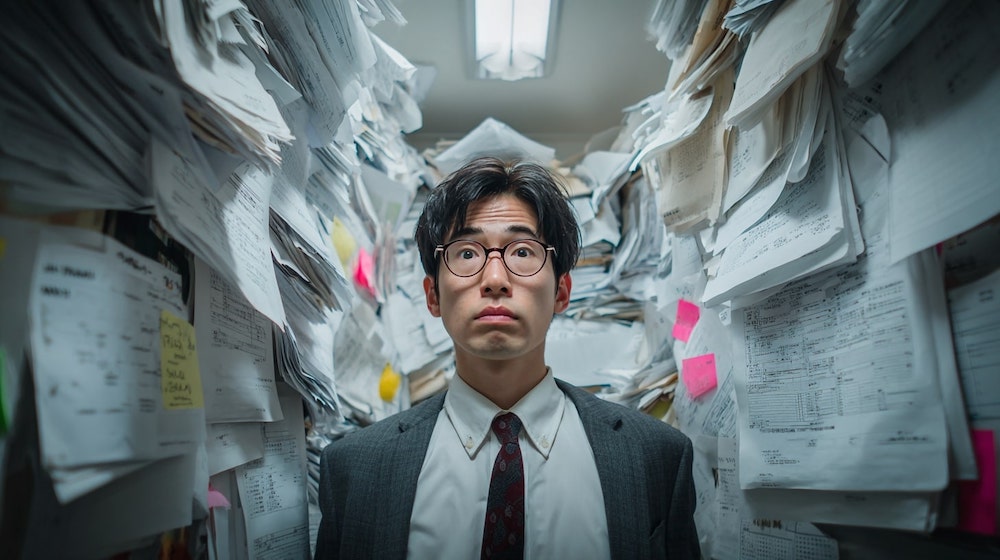こんにちは。ファイナンシャルコンサルタントの佐藤誠一郎です。
「ビジネスキャッシュ戦略」の著者として、また日本経済新聞「中小企業と金融」のコラムニストとして、多くの中小企業経営者の皆様と接してきました。
なぜ私が資金調達の専門家になったのか
私の原点は、三菱UFJ銀行(旧東京三菱銀行)で10年間、法人融資の担当者として過ごした時間にあります。
300社以上の中小企業の融資審査に携わるなかで、ある重要な気づきがありました。
多くの優れた経営者が、単なる「資金不足」ではなく「資金調達の知識不足」で苦労されている現実です。
その後、日本政策金融公庫で融資審査課長として勤務するなかで、この思いはさらに強くなりました。
銀行と企業の間には大きな「情報の非対称性」があり、本来なら融資を受けられるはずの企業が、単に「銀行の考え方」を理解していないために門前払いされているケースを数多く目の当たりにしたのです。
私が提供できる独自の視点
私の強みは、「銀行の目線」と「経営者の悩み」の両方を理解していることです。
銀行員時代に見てきた融資審査の現場。
そして政策金融機関での経験。
これらの知見をもとに、銀行が本当に見ているポイントをお伝えします。
例えば、多くの経営者は「赤字だから融資は難しい」と考えがちですが、実際の審査では「キャッシュフローの安定性」や「資金使途の明確さ」のほうがはるかに重要なことがあります。
水の流れがせき止められると別の道を探すように、資金調達も一つの道が閉ざされたら別の選択肢を探す必要があります。
私が提唱する「資金調達ポートフォリオ」の考え方は、銀行融資だけでなく、成長フェーズに合わせた多様な調達手段を組み合わせる方法論です。
私の方法論 — 理論と実践の架け橋
長年の経験から構築した独自の手法をいくつかご紹介します。
「3C資金調達分析」は、自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)を融資審査の視点から分析するフレームワークです。
これにより、銀行員が気にするポイントを先回りして対策できます。
また「銀行員の目線チェックリスト」は、実際の審査担当者が見ている40のポイントを整理したものです。
このチェックリストを使えば、融資申込前に自社の強みと弱みを客観的に評価できます。
資金調達の多様化とファクタリングの役割
中小企業の資金調達において、銀行融資だけに頼らない多角的な戦略が重要視されています。
その選択肢の一つとして注目されているのがファクタリングです。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を買取業者に売却して即日資金化できる手法で、審査のスピードや担保不要といった特徴があります。
しかし、ファクタリングには手数料の高さや業者選定の難しさなど、知っておくべき課題も存在します。
業界には優良な事業者がある一方で、不透明な取引条件を提示する業者も混在しているのが現状です。
資金繰りの選択肢を広げるためには、ファクタリング賛否両論 | プロが業界の表と裏を見た実情のような中立的な視点から業界の実態を理解することが大切です。
専門家による多角的な分析は、企業が最適な資金調達方法を選択する上で貴重な指針となるでしょう。
伝統から学ぶビジネスの本質
私は能楽(観世流)の愛好家で、40代から始めた茶道(裏千家)では師範資格も取得しました。
日本の伝統文化に親しむなかで、「本質を見極める目」と「無駄を省いた美しさ」を学び、それがビジネスコンサルティングにも活きていると感じています。
お茶の世界では「一期一会」の精神で、その瞬間を大切にします。
企業経営も同様で、目の前の資金繰りだけでなく、長期的な財務基盤の構築を見据えることが重要です。
私はこの考えを「ビジネスキャッシュ戦略」と呼んでいます。
経営者の皆様とのつながり
鎌倉市内の古民家を改装した自宅では、月に一度「経営者茶話会」を主催しています。
少人数の経営者と金融機関幹部が集い、お茶を囲みながら本音でディスカッションする場です。
形式張らない環境だからこそ生まれる気づきが、私自身の知見も深めてくれています。
これからの挑戦
日本の中小企業が直面している最大の課題は、「売上至上主義」から「キャッシュフロー経営」への転換だと考えています。
黒字倒産をなくし、持続可能な企業成長を支援するため、今後はより多様な業種にフォーカスした資金調達戦略の構築に力を入れていきます。
特に製造業以外、特にIT・サービス業の資金調達特性への理解を深め、より多くの経営者の皆様に実践的な知識を提供していきたいと考えています。
皆様の経営課題や資金調達のお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
銀行と経営者の架け橋となり、日本の中小企業の発展に貢献することが私のライフワークです。